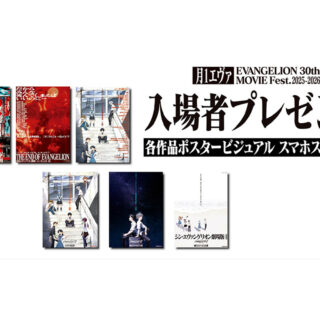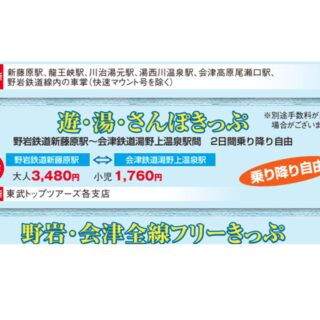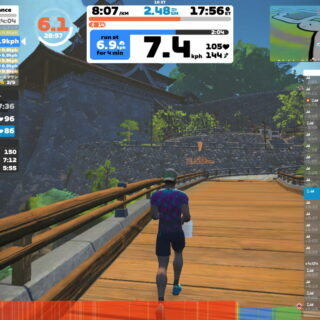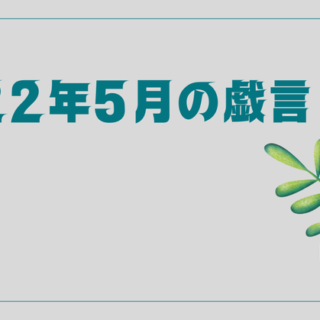「近鉄時代のことですが、
私が車掌として初めて北勢線に乗務したときのことです。
雨が急に降ってきたので窓を閉めたところ、
座っていた乗客の方たちが窓を閉め出し、
もののニ、三秒で全部の窓が閉まりました。
驚いたと同時に、北勢線は利用される地域の人たちに
とても親しまれている路線なんだなと感じました」
という三岐鉄道北勢運転区区長の嶋直樹さんのエピソードからも、
いかにも身近な路線であるのかがわかる。
路線の活性化を目指すさまざまな取り込み
近鉄から三岐鉄道へ北勢線を移管後、
経営の継続を図るために多岐にわたる改善や取り組みが施された。
車両の冷房化、駅の統廃合、駅舎のリニューアル、
改札の自動化、列車の高速化などのほか、
駅前に無料駐車場を設けてパークアンドライドの拡充も行われた。
また、鉄道自体を観光資源として捉え、
北勢線の特徴と沿線地域の特製を生かした利用促進にも力を注いできた。
たとえば、沿線で開かれる夏祭りと連動した前売り往復割引乗車券の販売や、
地元の特産品やグルメとからめたイベント列車の運行などの
旅客誘致を展開している。
今夏は北勢線開業一〇〇周年記念のスタンプラリーを実施している。
阿下喜駅に隣接する「軽便鉄道博物館」を
管理運営するASITA(北勢線とまち育みを考える会)会長の安藤たみよさんは
「座ると向かい合った人の膝が当たるといわれるほど狭い電車ですが、
それがアットホームで、魅力でもあります。
北勢線は地域に欠かせない鉄道です。
私たちも住民も存続に向けて
積極的に関わっていくことが大切と考えます」と話す。
三岐鉄道、行政、沿線住民の三者恊働による北勢線の活性化策は、
輸送人員をゆるやかながら上昇に向かわせ、
平成ニ十五年は三岐鉄道への移管後最高となる
約二四七万人の利用者実績を得た。
しかしながら赤字経営は依然解消には至っておらず、
今後さらなる乗客増が望まれている。
写真位置説明
1.三崎跨線橋から見た北勢線。
左から近鉄、JR、北勢線で、北勢線のレール幅は
762ミリ(ナローゲージ)と一般の鉄道に比べて狭い。
現在旅客営業しているナローゲージは
北勢線、近鉄内部線・八王子線、黒部峡谷鉄道の3路線だけである。
2.北勢線には47の橋梁があり、土木学会選奨土木遺産に認定された、
コンクリートブロック製のアーチ橋「ねじり橋」「めがね橋」が有名。
写真はJRと近鉄をまたぐ関西線跨線橋で、大正3年に建設された
3.北勢線の電化に合わせて製造されたモニ220形224号
4.かつての阿下喜駅舎。昭和6年の竣工ながら、モダンな意匠が目を引く
5.旧三重交通北勢線カラーに塗色された復刻車両。
平成25年10月29日より運行している。
6.発車前の安全確認
7.東員駅舎にある北勢線運転司令室
8.電車の運転席
9.三岐鉄道の嶋直樹さん。「北勢線には乗ってこそ味わえる楽しみがあります。
小さい車両ならではの大きな揺れと音。これがいいんですよ。
市街地の西桑名駅から、田園の広がる地域を抜けて、
山間の阿下喜駅への約1時間の旅は、まるで時代を遡るよう。
ぜひ車窓の風景をお楽しみください。」
10.ASITA(北勢線とまち育みを考える会)の
メンバーが制作した北勢線のミニ電車「ミニ電ホクさん」。
軽便鉄道博物館で乗車できる(無料)